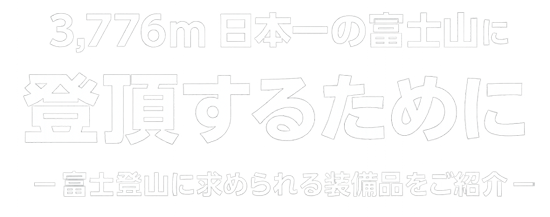富士山に挑むには
日本で一番高い山といえば、『富士山』。
普段、登山をしない人でも一度は登ってみたいと言われる日本の名山です。
富士山は登山ルートが複数あり登山道も整備されているため登山者も多く、比較的登りやすい山とも言われています。


ですが、富士山の標高は3,776m。
登りやすいとは言っても、3,000mを超える高山であることには違いありません。
登山経験がある人もない人も、登頂するためには必ず準備する装備品や注意点をしっかり確認してから富士登山にチャレンジしましょう。
※安全で快適な富士登山をサポートするために、2025年に富士山のルールが大きく変わります。
詳しくは富士登山オフィシャルサイト 「2025年 富士登山をするすべての方へ」を必ずご確認ください。

富士登山に必要な装備
必須アイテム
登山靴
足にフィットしたものを。必ず登山の前に履きならして足になじませておきましょう。
レインウェア
脱ぎ着しやすい上下が分かれた、セパレートタイプのものを選びましょう。防寒着としても使えます。※ビニールカッパ不可
防寒着
ダウンジャケット、フリース、セーターなど脱ぎ着のしやすいものを。絶対に忘れてはならない富士登山の必須アイテムの1つです。
ヘッドライト
御来光登山はもちろん、山小屋泊の小屋内でも必須です。天候の急変等で周囲が暗くなってしまう可能性もあるので、予備電池も忘れずに持ちましょう。
帽子・サングラス
陽射し・日焼け防止/熱中症対策に。森林限界を超えた登山道を歩く富士登山では、日差しを遮る帽子は必需品です。
水分
富士山に水道や水場はありません。山小屋の売店で購入することはできますが、あらかじめ500ml×2~3本程度の水は用意。高山病予防に、こまめな水分補給を心掛けましょう。
行動食
チョコや飴など、簡単に食べられるものをポケットに入れておきましょう。汗をかくので、塩分補給になるものも忘れずに。
非常食
万が一の事態に備えての非常食も持参しましょう。カロリーが高くかさばらないものがおすすめです。
現金(小銭)
有料トイレ用(1回200~300円)の百円玉を。携帯電話が使えない場合の電話代や、売店での買い物にも必要になります。
ゴミ袋
ゴミはゴミ袋に入れて、必ず全て持ち帰りましょう。
地図・コンパス
富士山には登山道がいくつかあります。たびたび下山時にルートを間違える問題が発生していますので、道迷いを防ぐためにも登山ルートは事前に確認しておきましょう。
常備薬・救急セット
普段飲んでいる薬や胃腸薬、ケガをした際の絆創膏や包帯など。
さらにあると便利なアイテム
トレッキングポール
ひざや腰への負担を軽減して歩行補助に役立ちます。4足歩行のように足への荷重負荷を分散できバランスも保ちやすくなるので、登りや下りがぐっと楽になります。
スパッツ
下山時に、靴の中に砂や小石が入るのを防いでくれるスパッツ。ズボンのすそが汚れるのも防いでくれます。
手ぬぐい・スポーツタオル
首回りの日焼け対策、汗ふき、さらには防寒対策にもタオル・手ぬぐいは持っていると重宝します。
マスク
富士山の登山道では、乾燥した地面や火山灰の影響により、風が吹いた際や登山者の通行によって砂埃が舞いやすい環境になっているため、携行・着用をおすすめします。
日焼け止め
富士山は紫外線が非常に強い場所です。できるだけ素肌を露出しないのが基本ですが、とくに首元や顔の急激な日焼けに注意が必要です。
着替え・替えの靴下
晴れた日は汗をかき砂埃を浴び、雨の日は泥汚れなどに見舞われる富士登山。下山時の着替えを忘れないように。
ウェットティッシュ
水道や水場などがない富士山では、手を拭きたい時、顔を洗いたい時などにウェットティッシュはとても便利です。
ヘルメット
転倒・落石などによる事故から頭部を保護するために、富士山ではヘルメットの装着が推奨されています。
OnePoint
その他にも、便利な持ち物リストはこちらからチェックしてください。
印刷してチェックリストとして活用できます。
富士登山に限らず、山では怪我をしてしまっても、すぐに救急車や助けが来てくれるというわけではありません。
山中にはコンビニやドラッグストアのような便利なお店もありません。
万が一の事態を考え、事前にしっかりと準備をしてから登るようにしましょう。

登山靴について
富士登山の前にちゃんと登山靴を履きならすと共に、
靴に足を慣らしておきましょう。
富士山は、登山道が整備されているとは言っても高山であることに違いありません。
しかも3,000m級の日本で一番高い山です。
樹林帯を抜け、森林限界も超えると植物の生えない岩場を迎えます。
不安定な足場が連続的に続く中で、転倒して怪我をしないよう足元をしっかりと支えてくれる、自分に合った登山靴を用意しましょう。
富士登山での靴選び。チェックしたいポイントとは
履き口はミドルカット以上がおすすめ!
登山靴の履き口は必ずしもミドルカットである必要はありませんが、捻挫のリスクを考えて足首をしっかりホールドしてくれて、整備されていない道も歩きやすいミドルカット以上の靴を選びましょう。
登山初心者の方には足首が動きやすいよう、アキレス腱部分を浅くカットしたトレッキングシューズが使いやすく、おすすめです。


ソールが曲がりすぎず、捻じれに強い
富士登山の場合は、本格的な登山靴のように硬いソールは必要ありません。けれど、スニーカーのような柔らかいソールが適している訳でもありません。
足にぐっと力を入れるとソールが曲がる程度の硬さのものが良いでしょう。
また、ねじれに弱いソールの場合は履き口のカットが高いものでも歩く際の安定感に欠けてしまい、捻挫などのリスクが増えてしまいます。
実際に登山靴に触れて確かめてみましょう。
履き口(足首)周辺の柔らかさ
富士登山では、履き口が硬くカッチリしたものは必要ありません。逆に、登山に慣れていない人の場合は履き口が硬いものを選ぶと、足が痛くなってしまい歩きにくくなる場合もあります。
足首が擦れないように、履き口がソフトな登山靴を選ぶと歩きやすいでしょう。登山靴を履く際は必ず、登山用のソックスを着用するよう心掛けましょう。

富士登山 おすすめトレッキングシューズ
登山用ソックスについて
「普段履いているソックスでも大丈夫なんじゃないの?」と思われがちなソックスですが、登山用ソックスを選ぶことで登山の快適さは格段に変わります。
登山用のソックスを持っていない場合は、まずは登山用ソックスを履いてから登山靴を選ぶことをおすすめします。
登山の前にトレッキングシューズを履きならす際、一緒に履いて登山用ソックスにも慣れておきましょう。
登山でソックスに求められる機能
- 擦れ防止・・・適度な厚さのソックスは、足首周辺の擦れを防止してくれます。
- 適度な保温性・・・夏でも平均気温が7~8℃と言われる富士山。適度な保温性で汗をかきすぎず、汗冷え防止にもなります。
- クッション性・・・インソールに加えて登山用ソックスを履くことでクッション性が得られ、足が疲れにくくなります。
- 吸汗速乾性・・・足汗をかいたとき素早く汗を吸収して足裏をドライに保ちます。靴内が蒸れすぎると皮がふやけて思わぬケガを招きます。

より快適になるソックスの機能
- 吸汗・速乾・・・汗を吸い、発散させてくれる登山用ソックスは、足の冷えを防いでくれます。
- メリノウール使用・・・メリノウールには天然の防臭効果があり、2日間続けて使用しても臭いが気になりにくいのが特長です。
- 右足・左足専用設計・・・手と同じで足も左右の形状が異なります。左右それぞれの足に合わせた形で、よりソックスのズレが少なく快適で歩きやすくなります。
富士登山 おすすめソックス
RLメリノ・レトロトレッキング
メリノウール・パイルソックス
RLドライノヴァ・マダラックス
RLドライノヴァ・マダラックス・TABI
ポールについて
歩きやすさが変わる!トレッキングポール
富士山に登る際、トレッキングポールが必ず必要かと言われれば、そのようなことはありません。ですが、有ると無いとでは歩きやすさが違います。
登山時の下半身への負担軽減、下山時の膝への負担軽減、荷物の重さをポールに分散できる、バランスがとりやすくなるなどのメリットがあり、疲れを軽減することもできるので非常におすすめです。


ですが、約400~500gほどの重量があること、使わないときにかさばってしまうことなどの煩わしさもあります。
できるだけ軽量かつ丈夫、そして折りたためるものなどタイプの異なるトレッキングポールの中から、自分に合ったモデルを選びましょう。
こちらもチェック


富士登山 おすすめトレッキングポール
スカイ テラ FX カーボン
マカルー FX カーボン
クレシダ FX カーボン
レガシーライト PRO AS
その他アイテム
レインウェア
「山の天気は変わりやすい」と昔からよく言われているように、山の天気はいつどのように急変するか分かりません。
たとえ雨が降っていなくても雲の中に入れば、全身が濡れてしまうこともあります。また、風が強い場合にレインウェアは風よけになる場合や、防寒着として使うこともできるので、登山では必需品です。
ビニール素材などの簡易ポンチョではなく、上下セパレートタイプのものを選ぶと脱ぎ着も簡単です。


防水・透湿素材を使用したものを選びましょう
登山中にかいた汗を逃がしつつ、雨を防いでくれる機能性があります。
汗が逃げないビニール製のレインウェアでは透湿性がないため、ウェア内の湿気が抜けず立ち止まったりした際などに汗で体が冷えてしまう危険性が高くなります。
防寒着・ウェア
標高が高くなれば、その分気温は下がります。また、風雨の場合は風冷効果などで体感温度も下がります。
富士山は3,000m級の高山です。標高が高いため、開山期間の7月頃から9月上旬にかけてでも平均気温が7~8℃と言われています。
普段使用しているスウェットなどの防寒着でも代用は出来ますが、綿のウェアは生地が汗を吸収して乾かず、汗冷えに繋がるため避けるようにしましょう。
軽量でコンパクト性に優れるダウンウェアやフリースウェアがおすすめです。
防寒着は使用するまで雨などで濡れたりしないように、ビニール袋やドライサックなどで防水対策を施しておきましょう。

濡らしたくない荷物を入れる、
便利なドライサック
バックパックの中で様々な荷物がバラバラになったり、どこにあるか分からくなったり……という事態を防いでくれるのが、スタッフサック。その中でも、防水性に優れた『ドライサック』を使用することをおすすめします。
防寒着やレインウェア、タオルや着替えなど、ある程度くしゃくしゃになっても問題のないものは、小さくまとめてパック内で仕分けして収納しておくと良いでしょう。




タオルや手ぬぐい、着替えをまとめてコンパクトに!
NeoShellドライサック(5L~25L)は、底の部分にポーラテックのネオシェルを採用しています。
パッキングの際、いちいち空気を抜く「巻き戻し」が不要。底のネオシェル部分から驚くほどスムーズに空気を抜くことができるため、簡単にコンパクトパッキングができます。
防水サックなので、山中で一時的に濡れたものを入れることもできます。ただ、濡れた衣類やタオルなどをドライサック内に長時間入れておくと内側に施したシームテープが剥離しやすくなるので、基本的には”濡らしたくないもの”をドライサックに入れるようにしましょう。
予備分を含めていくつかサイズの異なるドライサックを持っておくのも良いでしょう。
砂埃や火山灰の吸い込みを防ぐマスク
富士山の登山道では、乾燥した地面や火山灰の影響により、風が吹いた際や登山者の通行によって、砂埃が舞いやすい環境となってます。
特に、登山道が混雑する時間帯や下山時には、前方の登山者が巻き上げた砂埃が顔にかかる事もあり、のどや鼻からの吸い込みを防ぐためにもマスクの携行・着用をおすすめします。


いざとなったら防寒具にも?タオルや手ぬぐい
汗を拭いたり顔を洗ったり、下山後の温泉で使ったりと、あると何かと便利なタオルや手ぬぐい。接触冷感機能のあるタオルなら、首元を冷やして熱中症対策としても活躍してくれます。
また、速乾タイプのタオルなら濡れても絞れば簡単に水分を排出してくれるので乾きも早く、一枚持っているだけでとても便利。急な雨などにも活躍します。


落石・転倒事故から頭を守るヘルメット
富士登山の際にはヘルメットを装着することが、公式に推奨されています。
人気が高く、様々な人が登る富士山ですが、実は富士山はかなり危険な山でもあります。
落石事故や転倒事故は、実際に自分がどれだけ気をつけていても起こるもの。そういった事故が起きた時、頭部を守るためにヘルメットの装着が強く推奨されているのです。
自分自身を守るためにも、ヘルメットを用意していくことが望ましいでしょう。


砂や石が入るのを防いでくれるスパッツ
スパッツは下山時に、履き口から靴の中へ砂や石が侵入するのを防いでくれます。悪天候の後のドロ跳ねも防ぐ役割もあります。
また、足首をすっぽりと包んでくれるスパッツは、体温が下がるのを防止してくれる効果もあります。
雨や泥をよけるために、防水性のものをおすすめします。

登山前の事前準備はしっかりと!
登山において、「服装や装備から入るのは邪道!」ではありません。
自分の身体にフィットした背負いやすいバックパックや雨風から守るパックカバー、レインウェアやトレッキングポール。そして、なんと言っても一番重要な歩きやすい登山靴。
準備が整ったら、実際に富士登山に挑むまでに、それらの道具の使い方をしっかりと把握し使いこなせるようにしておくことが肝心です。
そして登山靴は何度も実際に履いて歩いて、足に馴染ませておきましょう。
富士山に登ったという大切な思い出が、準備不足で残念なものにならないように、できるかぎり準備は万全を心掛けましょう。